近年、富士市のみならず全国的にもお坊さんを呼ばない「無宗教葬」や「自由葬」が増えてきているようです。
宗教色を減らし、故人や遺族の想いを最大限に反映するスタイルは、ごく少人数の家族葬であったり、音楽や思い出を語るセレモニースタイルまで多様です。
ここではそんなお坊さんがいないお葬式に関し、費用、形式、菩提寺との関係などを紹介したいと思います。
「お坊さんがいないお葬式」とは?
「お坊さんがいないお葬式」とは、宗教儀礼や読経・戒名を伴わず、遺族や参列者が主体となって行う葬儀スタイルです。無宗教葬、自由葬、直葬など形式は多岐に渡ります。
つまり今までのお葬式のスタイルとは異なった葬儀スタイルとなります。
無宗教葬・自由葬と一般的なお葬式の違い
- 無宗教葬/自由葬:読経なし、司会進行や献花、音楽演出を取り入れ、故人の人生を表現するセレモニー形式。
- 一般的なお葬式:通夜・告別式が基本的にはある(どちらか、もしくは両方省略もある)。搬送→安置→通夜→告別式→火葬→収骨の流れ。
種類別の特徴比較
| 形式 | 特徴 | 代表的な流れ |
|---|---|---|
| 自由葬 | 音楽やスライド上映など自由な演出が可能 | 開式 → 生演奏・映像 → 参列者の思い出語り → 献花・黙祷 → 閉式 |
| 火葬式/直葬 | 儀式なし、火葬に特化 | 搬送→安置→通夜→告別式→火葬→収骨 |
メリット
お坊さんを呼ばないことで費用を抑える自由が生まれ、心を込めたセレモニーを追求しやすくなります。
費用が抑えられる
お坊さんへのお布施(戒名料含む)は20〜50万円が相場であり、年忌法要への費用も継続的に発生。これを省くことで全体の葬儀費用が大きく軽減されます。
また呼ぶお坊さんや戒名のつけ方によっては、もっと高い金額が必要となるケースもあります。
セレモニーを自由にカスタマイズできる
宗派や儀礼に縛られず、故人ゆかりの音楽や映像、献花など独自の演出が可能です。親しい人たちとアットホームな時間を共有できます。
心的負担の軽減
普段関係のない僧侶と初対面で儀式を行うストレスがなく、家族巻き込んだ見送りに集中できます。
デメリット
一般的ではないため、親族や知人、さらには菩提寺などから理解を得られない可能性があります。
菩提寺・納骨の確認が必要
菩提寺がある場合、無宗教葬では納骨を断られる可能性があります。事前に「お坊さんなしでも納骨可能か」を確認し、公営・民営霊園の選択も検討が必要です。
親族・参列者の理解
従来の葬儀に慣れている人には、葬儀のスタイルが一般的ではないという理由から「非常識」「手抜き」と受け取られる可能性もあります。遺族同士で相談し意向と理由を共有することが大切でしょう。
儀式構成が難しい
定型的な進行でないため、葬儀社も困惑してしまう可能性があります。自分たちで場の区切りやプログラムを考える手間が発生。居心地の良い式にするには事前準備や台本作成などが欠かせません。
利用する予定の葬儀社に足を運び、そもそも「無宗教葬」や「自由葬」が可能かどうか、進行はどのような形が良いのかなどを相談してみるとよいでしょう。
お坊さんなし葬儀に向いている人
お坊さんがいないタイプのお葬式には、以下のような方が向いているかもしれません。
菩提寺付きではない世帯
菩提寺との関係が薄い場合、無宗教葬が選びやすく納骨の選択肢も広がります。
家族だけで静かに見送りたい方
参加者が少人数で、気兼ねなく故人を偲びたい場合に適しています。
これが理由の場合、家族葬なども選択肢に入ってくることでしょう。参列者を制限することはできます。
オリジナルな演出を望む方
生演奏、映像会、キャンドルなど、個性的なセレモニーを希望する方に最適です。
お坊さんなしで後悔しないためのポイント
不安や後悔を避けるために、以下の点をしっかり確認・準備することが大切です。
遺族間で意向を共有
「なぜお坊さんなしにしたいか」「どんな式にしたいか」を明確化し、家族内で共通理解を持つことが重要です。
菩提寺・納骨先への事前確認
菩提寺とはコミュニケーションを取り納骨可能かどうかを確認。問題がある場合は、宗旨問わない霊園や永代供養を検討してもよいでしょう。
参列者への配慮
形式変更を知らせておくことで、当日の戸惑いやトラブルを防止できます。
積極的な演出準備
司会進行、映像・音楽選定、台本作成など、遺族や葬儀社と協力し安心して見送れる進行設計をしましょう。
具体的な進め方とチェックリスト
迷わず進められるよう、段取りをステップに分けてご紹介します。
初期段階
- 家族で形式(無宗教/直葬等)を決定
- 参列範囲と希望演出(音楽・映像等)を共有
- 菩提寺・納骨先の確認
葬儀社打ち合わせ
- 時間・人数・会場形式を明確化
- 台本・進行表を作成
- 司会・進行役担当の検討
準備段階
- 映像・写真、選曲の収集
- 弔辞者への依頼状況把握
- 献花やお別れグッズの手配
当日と火葬後
- 式前の動線・挨拶の段取り確認
- 献花・黙祷などプログラム進行
- 火葬後の収骨までのフォロー
初期段階より葬儀社に相談してもよいでしょう。最近では自由葬が増えているため、これまでどのようなタイプのお葬式が取り扱ってきたのかを教えてくれます。
よくある質問
Q. お坊さんなしで葬式をしても非常識では?
A. 社会的慣習は変わってきていて、故人やご家族の意思を尊重する形のお葬式は今や一般的です。事前に理解が得られれば問題ありません。
Q. 成仏できない?バチが当たる?
A. 仏教の一部にはそうした考え方もありますが、現代では「心を込めたお見送り」が重要視されています。
Q. 遺族が儀式進行できるか不安です・・・
A. 遺族が進行する必要はありません。葬儀社のスタッフが進行してくれます。
まとめ
お坊さんがいない葬儀は近年増えてきています。
費用削減や個別の想いを尊重しやすい一方、今までのスタイルとは異なったスタイルを採用するため、親族側の事前の準備、そして負担は多くなることでしょう。また菩提寺や親族の理解も必要になってくることでしょう。
後悔しない式にするためには、遺族間での意思統一、納骨先の確認、進行準備が重要でしょう。

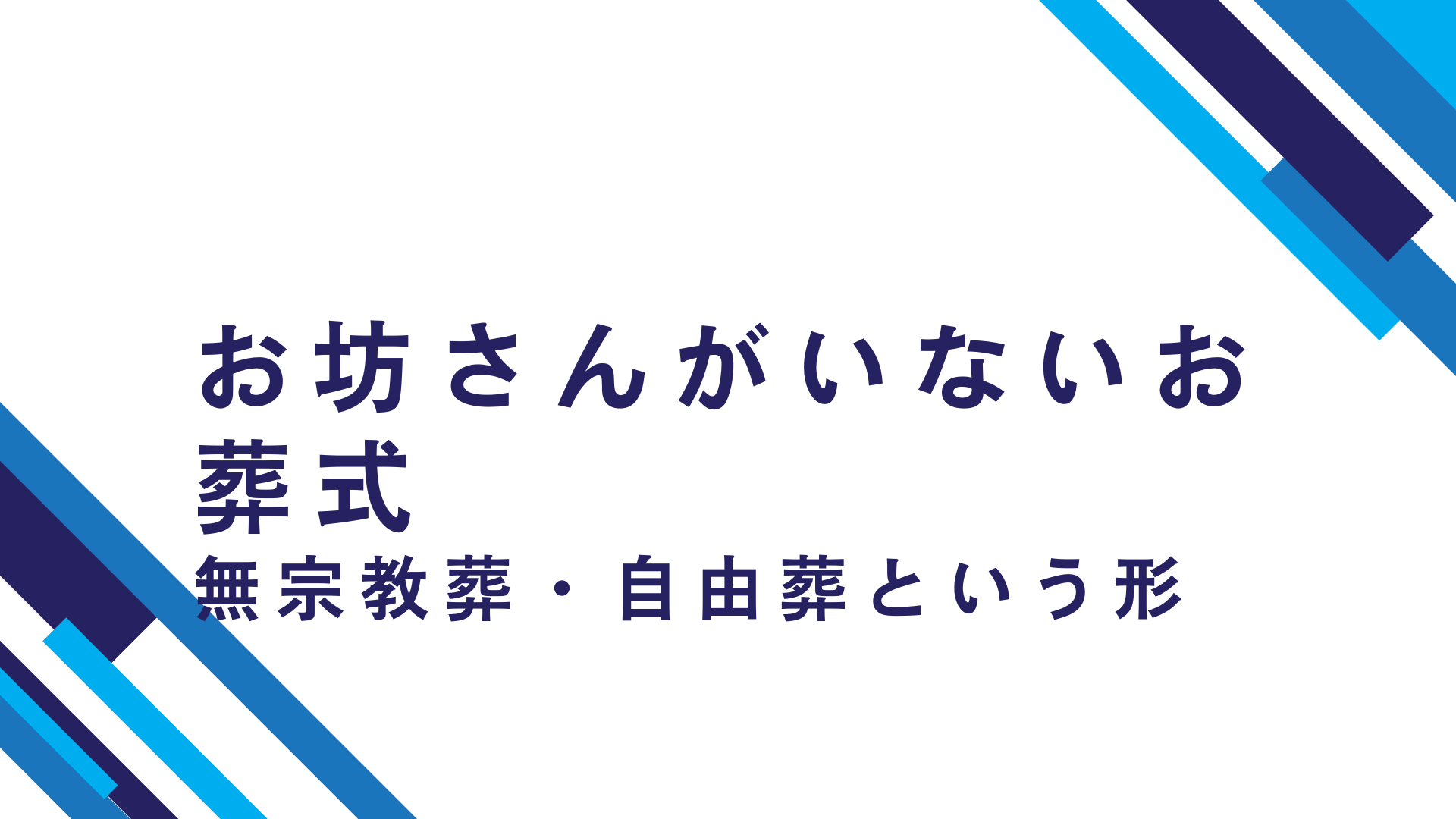



コメント